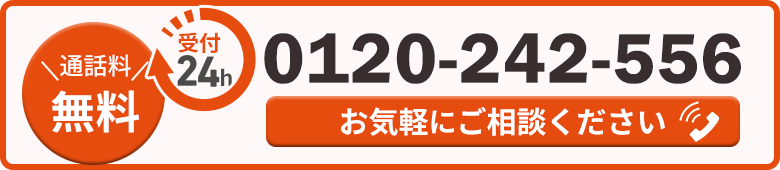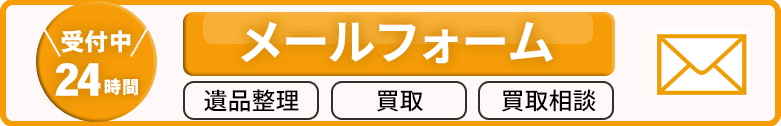カメラの寿命は?種類別の目安や寿命を長くする方法も解説!

カメラにはさまざまな種類があり、使い方や保管環境、メンテナンス状況によって寿命は大きく変わります。
たとえば一眼レフの場合、目安として5~6年ほどと言われることが多いですが、使用頻度や故障のリスク管理によってはさらに長く使えることもあります。
この記事では、種類別におおよその寿命や、寿命を迎えたカメラの特徴を詳しく解説します。使い続けるリスクや寿命を延ばすための日頃のメンテナンス方法、そして寿命を迎えた際の処分方法や買取の選択肢についても取り上げます。
なお、累計買取実績数300万点超えのウリエルでは、カメラの無料査定を実施中。査定をご検討の方は以下のメールや電話からお気軽にご相談ください。豊富な知識と確かな目利きを持つ査定士があなたのお品物の価値を正確に査定いたします。

ウリエル 商品管理スペシャリスト
河合拓治
リユース業界で12年のキャリアを持ち、現在は買取ウリエルのロジスティクスセンター責任者として年間数万点に及ぶ商品の流通・管理を統括しています。リユース検定や酒類販売管理者の資格を保持し、特にダイヤモンド・ブランド品・着物の管理体制構築に精通。
現場では「複数人による多角的な検品」を徹底し、個品管理による匂い移り防止や破損対策など、商品の価値を損なわないためのオペレーションを追求しています。物流コストの最適化を通じて、お客様への還元率向上に貢献することを目指しています。
監修者の詳細はこちら
目次
【種類別】カメラの寿命

カメラの種類ごとに寿命の目安や注意点が異なります。一眼レフカメラのようなプロ仕様の機材から、子ども向けのキッズカメラまで、それぞれの設計思想や使用目的によって、耐久性や部品の品質などには大きな差があります。
代表的なカメラは以下の通りです。
- ・一眼レフカメラ
- ・ミラーレスカメラ
- ・コンパクトデジタルカメラ
- ・フィルムカメラ
- ・防犯(トレイル)カメラ
- ・アクションカメラ
- ・キッズカメラ
- ・チェキカメラ
ここでは、これらのカメラの寿命について詳しく解説します。
一眼レフカメラ
一眼レフカメラはシャッター機構を備えており、シャッターユニットの耐久回数が約10万~20万回以上とされています。上位機種の場合、さらに高い耐久性を持つものも多く、プロ向けモデルであれば40万回程度を目安に作られている場合があります。
バッテリー劣化も大きな要因となるため、定期的に予備バッテリーを含めた管理が大切です。
一眼レフカメラの寿命を左右するもう一つの重要な要因は、メーカーによる部品供給期間です。国内主要メーカーでは、製造終了からおおよそ7~8年間は修理用部品を保有しており、この期間内であれば故障時の修理対応が可能です。
海外メーカーのライカなどは、部品在庫がある限り修理対応を継続する方針を取っており、数十年前の機種でも修理が可能な場合があります。
ミラーレスカメラ
ミラー機構がない分、機械的なトラブルは少なく軽量でコンパクトなのが魅力です。しかし電子部品や液晶パネルの故障リスクがあり、センサーへのホコリやカビなどによって画質に影響が出る場合もあります。
ミラーレスカメラの寿命を決定づける最も重要な要因は、電子ビューファインダー(EVF)と背面液晶モニターの劣化です。
これらの表示デバイスは常時稼働するため、一眼レフカメラの光学ファインダーと比較して電力消費が大きく、バックライトの寿命や液晶パネルの劣化が本体寿命に直結します。
シャッター機構については、エントリーモデルで5万回、上位機種で20万回程度の作動回数が設計上の目安となっています。
バッテリー寿命を伸ばすためには、保管前に取り外しておく、適切に充電するなどの工夫が重要です。
コンパクトデジタルカメラ
軽量で取り回しやすい反面、防水や防塵機能がないモデルは内部にホコリや湿気が入りやすい傾向があります。特にレンズの繰り出し機構が故障すると撮影が困難になるため、ケースに入れるなどして衝撃や汚れから保護することが大切です。
シャッターユニットやバッテリー性能が寿命を左右する点は、一眼レフやミラーレスと共通しています。
コンパクトデジタルカメラは、一眼レフやミラーレスカメラと比べると短命です。その理由は、価格競争により部品品質が抑えられているためです。
シャッターユニットの耐久性は公表値が少ないものの、近年のモデルではおおむね3万回~5万回以上の耐久性があります。
レンズの駆動機構も簡素化されており、ズーム動作やフォーカス動作の繰り返しにより、2~3年で動作不良を起こす可能性もあります。
フィルムカメラ
フィルムカメラは機械式の構造が多く、定期的にグリスを塗布し部品を点検すれば数十年使用できる場合があります。
フィルムカメラが長寿命である最大の理由は、その純機械的な構造にあります。電子部品への依存度が低く、シャッター機構、露出計、フォーカス機構のすべてが機械的に動作するため、電子的な故障リスクが極めて低くなっています。
特に1970年代以前に製造された、電池を使わないセレン光電池式露出計や完全機械式シャッターを備えるフィルムカメラは、メンテナンス次第では50年以上使える例もあります。
とはいえシャッター幕や内部のギアが損傷すると修理費がかさむこともあるため、古いモデルを使い続ける場合は専門の修理業者でのメンテナンスが欠かせません。パーツが入手困難になると修理が難しくなるので、早めの点検が大切です。
防犯(トレイル)カメラ
屋外設置が多いため、雨や雪、直射日光による経年劣化が他のカメラよりも進みやすいです。定期的に防水シーリングやケースの密閉具合をチェックし、バッテリーの状態も確認することが必要となります。
防塵防滴性能(IPX6以上)を持つ機種でも、シーリング材の劣化により3~4年で防水性能が低下し、内部への水分侵入リスクが高まります。防水性能が低下すると内部の電子部品が故障し、カメラ全体の寿命を縮めてしまうおそれがあります。
防犯カメラの寿命を大きく左右するのは、24時間365日の連続運用による電子部品への負荷です。イメージセンサーは常時稼働状態にあり、熱による劣化が進行しやすく、2~3年で画質の低下が起こる可能性があります。
特に夏季の高温環境では、センサーノイズの増加や色再現性の変化が起こりやすく、撮影画像の品質維持が困難になります。
アクションカメラ
スポーツやアウトドアでの使用を想定して作られており、衝撃や防水に強い設計が特徴で、寿命は3~5年程度が一般的です。ただしハードな使用が続くと外装の破損やレンズのひび割れ、バッテリーへのダメージも受けやすくなります。
アクションカメラの寿命を決定する最も重要な要因は、超小型筐体に高性能な電子部品を詰め込むことによる熱問題です。
4K動画撮影時には、イメージセンサーと画像処理チップが大量の熱を発生し、狭い筐体内での熱蓄積により電子部品の劣化が急速に進行します。
連続撮影時間の制限は熱対策の一環ですが、それでも2~3年の使用でバッテリー膨張やセンサーノイズの増加が発生する可能性があります。
定期的に傷や汚れをチェックして早めに対策することで、アクションカメラの寿命をできるだけ延ばすことができます。
キッズカメラ
寿命は1~3年程度が一般的で、子ども向けの簡易設計で扱いやすい反面、耐久性はそれほど高くありません。
キッズカメラの寿命が短い最大の理由は、製造コストを抑えるための部品選定にあります。
シャッター機構は簡素化されており、耐久回数は十分に設定されているものが多いですが、子どもの好奇心による頻繁な撮影により、半年から1年程度で動作不良を起こすことがあります。
ボタン類は操作が簡単になるよう大型化されていますが、その分壊れやすく、押しボタンの陥没や接触不良が発生する可能性があります。
レンズも固定焦点の単純な構造で、精密な調整機構を持たないため、落下や乱暴な使い方で破損するリスクがあり、電子部品への負荷も大きいです。子どもにカメラを渡す場合は、ストラップやクッション性のあるケースで保護することが重要です。
チェキカメラ
インスタントフィルムを使用するチェキカメラでは、フィルムを搬送するためのモーターやバッテリー駆動部分が壊れると撮影できなくなります。
ローラー部分は現像液を均等に塗布する役割を担っており、この部分の摩耗や汚れの蓄積により、現像ムラや送り不良が発生します。特に使用頻度の高い環境では、2~3年でローラー表面の劣化が起こる可能性があり、写真品質に影響が現れます。
フィルムパック交換時に現像液が微量に漏出し、カメラ内部の金属部品を腐食させる問題もあります。この腐食は徐々に進行し、5年程度でフィルム室の密閉性が低下する可能性があり、露光や現像に悪影響を与えます。
電池切れや保管環境の影響を受けやすく、温度や湿度が極端な場所での保管は避ける方が無難です。定期的に動作確認を行い、異常があれば早めに修理や買い替えを検討した方が良いです。
寿命を迎えたカメラの特徴

カメラが寿命を迎えると、さまざまな不具合や異常が生じるようになります。複数の症状が同時に現れる場合や、症状が進行性である場合は、寿命のサインとして認識する必要があります。
具体的にどのような症状が現れるのかは以下の通りです。
- ・電源が入らない・不安定
- ・シャッターが切れない・遅い
- ・エラーメッセージが頻繁に出る
- ・レンズの動きがおかしい
- ・記録できない・データが消える
- ・バッテリーの持ちが極端に悪い
- ・異臭や異常な発熱
ここでは、これらの寿命を迎えたカメラの特徴について詳しく解説します。
電源が入らない・不安定
突然全く電源が入らなくなる、あるいは撮影中に電源が勝手に落ちるといった症状は、バッテリーや内部回路の故障が考えられます。
カメラ内部では、バッテリーからの直流電圧を各部品に適した電圧に変換する複数の電源回路が動作しており、これらの回路に使用されているコンデンサや抵抗器が経年劣化により機能低下を起こします。
購入してから数年経ち、バッテリーを一度も交換していない場合は劣化を疑ってみるとよいです。
電源管理IC(集積回路)の故障は、深刻な症状です。現代のデジタルカメラでは、バッテリー残量監視、充電制御、各部への電力配分を専用ICが管理しており、このICが故障すると電源系統全体が機能停止します。
IC自体は表面実装部品のため交換作業が困難で、基板全体の交換が必要になることが多く、修理費用が本体価格を上回る場合がほとんどです。
シャッターが切れない・遅い
シャッターボタンを押してもレンズが反応しなかったり、明らかにタイムラグが大きかったりする場合はシャッターユニットやセンサーの故障が考えられます。異音がする場合も同様で、即座にメーカーや修理業者への相談が必要です。
シャッターユニットの機械的摩耗は、最も典型的な症状です。現代のカメラでは、薄い金属製の幕が高速で移動することでシャッター動作を実現しており、材質劣化や駆動機構の摩耗により動作不良が発生します。
エントリーモデルでは5万回、上位機種でも30~50万回の耐久設計ですが、実際の使用環境では設計値より早期に摩耗することがあります。
シャッター駆動モーターの劣化の場合は、初期症状としてシャッター音の変化や動作速度の低下が現れ、進行すると動作停止します。特に高速連写を頻繁に使用する場合、モーターの劣化が早くなります。
エラーメッセージが頻繁に出る
メモリーカードとの接触不良やレンズ接点の傷などでエラーが多発する場合、内部の基板やコネクタ部分の劣化が疑われます。
メモリアクセスエラーは、画像処理用のRAMや一時記憶領域に不良セクターが発生すると、データの読み書きが正常に行えず、撮影処理中にエラーが発生します。
初期段階では特定の撮影モードでのみエラーが出現しますが、不良箇所が拡大すると全ての機能でエラーが頻発するようになります。
レンズ通信エラーの多発は、マウント部の接点劣化を示しています。カメラボディとレンズ間では、絞り制御、フォーカス制御、手ぶれ補正制御などの複雑なデジタル通信が行われており、接点の汚れや腐食により通信エラーが発生します。
そのまま放置するとさらに重大な故障を引き起こす可能性があるため、早期の点検が望まれます。
レンズの動きがおかしい
オートフォーカスが突然作動しなくなったり、ズームが引っかかったりするように感じる場合はレンズ内部のモーターやギアが故障している可能性があります。
オートフォーカス機構の劣化は、最も頻繁に発生するレンズ系統の不具合です。AFモーターには超音波モーター(USM)やステッピングモーターが使用されており、これらのモーター内部の磁石劣化やコイル断線により駆動力が低下します。
初期症状として、フォーカス動作の遅延や迷いが発生し、進行すると特定の距離でのフォーカシングが不可能になります。特に望遠レンズでは、重いレンズ群を駆動するため負荷が大きく、3~5年で駆動力不足による症状が現れることがあります。
外部からの衝撃やゴミの混入によってもトラブルが発生するため、レンズ部分はとくに注意して確認することが重要です。
記録できない・データが消える
撮影した写真がメモリーカードに保存されない、あるいはデータが破損して読み出せなくなる症状は深刻です。カメラ側の書き込み機能やメモリーカードスロットが故障し始めている可能性が高いため、早めのバックアップと修理対応を行うべきです。
SDカードやCFカードへのデータ書き込みを制御する専用ICが劣化すると、正常なメモリーカードを使用していても書き込みエラーが頻発します。
初期段階では、特定のファイルサイズや撮影モードでのみエラーが発生しますが、劣化が進行すると全ての撮影でエラーが発生し、最終的には一切の記録ができなくなります。
画像処理エンジンの不良により、撮影されたRAWデータをJPEGに変換する画像処理プロセッサーが劣化すると、処理中にデータが破損する可能性もあります。
バッテリーの持ちが極端に悪い
新しく充電したはずなのに、すぐにバッテリー切れになってしまう場合はバッテリー自体の限界か、内部の充電回路が問題になるケースがあります。
バッテリーの場合は、充放電サイクルの繰り返しにより、内部の電極材料が劣化し、蓄電容量が減少したことが要因です。
カメラ用リチウムイオンバッテリーの寿命は100~500回程度の充放電サイクルが一般的とされています。取り扱いによっては若干長持ちする場合もありますが、一般的に毎日充電した場合、1年~2年程度で性能が低下します。
カメラ本体の電力制御回路の劣化も、バッテリー消費に影響を与えます。電圧レギュレーター回路が劣化すると、必要以上の電力を消費するようになり、同じバッテリーでも撮影可能枚数が減少します。
予備バッテリーを使用してチェックし、本体側の異常も含めて慎重に判断することが重要です。
異臭や異常な発熱
操作中に焦げくさいにおいがする、異常に筐体が熱くなるといった症状は非常に危険です。電子部品のショートや配線の断裂が発生している可能性があるので、直ちに使用を中止して専門業者に相談した方が良いです。
化学的な刺激臭がする場合は、電子回路基板の過熱による樹脂部品の熱分解が原因です。この時に発生する物質は人体に有害で、密閉された室内での撮影中に吸引すると、頭痛、めまい、呼吸困難などの急性中毒症状を引き起こします。
モーター駆動系統の機械的摩擦による発熱も、深刻な安全リスクを生じさせます。オートフォーカスモーターやシャッター駆動モーターの軸受け部分が劣化すると、異常な摩擦により金属粉が発生し、特有の金属臭を放ちます。
この金属粉が電子回路に付着すると、ショートの原因となり、スパークによる発火リスクが生じます。
寿命を迎えたカメラを使い続けるリスク

不調の兆候があるカメラを無理に使い続けると、撮影機会を逃すだけでなく、さらなる大きなトラブルを招く可能性があります。小さな不具合を見過ごしているうちに、パーツの連鎖的な故障が起こるケースもあります。
寿命を迎えたカメラを使い続けるリスクは以下の通りです。
- ・決定的な撮影機会を失う
- ・データの損失・破損につながる
- ・余計な修理費用や買い替え費用が発生する
- ・事故や怪我のリスクにつながる
ここでは、これらのリスクについて詳しく解説します。
決定的な撮影機会を失う
家族行事や旅行などの思い出を撮り損ねるだけでなく、業務で使用している場合はビジネスチャンスを逃すことにもなります。
例えば家族写真において、失われた瞬間の価値は計り知れません。高齢の祖父母との最後の家族写真や、遠方に住む親戚との久しぶりの再会写真など、家族の絆を表す貴重な瞬間は、二度と同じ状況を再現することができません。
商業撮影では、撮影機会の損失が直接的な経済損失につながります。モデルやスタッフのスケジュール調整、スタジオやロケ地の手配、照明機材の準備など、一回の撮影には多大な時間とコストが投じられています。
カメラの故障により撮影が中断された場合、これらの費用が全て無駄になるだけでなく、クライアントとの信頼関係にも深刻な影響を与えます。
カメラの不調は、いつ重大な場面で発生するか分からないため注意が必要です。
データの損失・破損につながる
撮影後にデータが読めなくなる、急にメモリーカードを認識しなくなるなどの症状は、大切な画像を失う原因となります。それどころか、ファイルシステムの破綻は、メモリーカード全体のデータを同時に失う壊滅的な結果につながる可能性もあります。
カメラ内部の記録制御回路が不安定になると、書き込み処理中にファイルアロケーションテーブルが破損し、メモリーカード内の全てのデータにアクセス不能になることがあります。
数ヶ月分の撮影データを保存したメモリーカードが一瞬で使用不能になった場合、専門業者によるデータ復旧作業が必要になりますが、完全復旧の保証はなく、費用も高額になります。
バックアップをこまめに取ることはもちろん、カメラ本体の異常を早期に見極めることが肝心です。
余計な修理費用や買い替え費用が発生する
部品の多くが故障すると修理が複雑化し、結果的に新品同様の金額を払うはめになることもあります。
応急処置的な修理の繰り返しも、根本的な解決に至らず累積的な高額出費となります。寿命を迎えたカメラでは、一つの部品を修理しても他の部品の劣化が連鎖的に表面化し、その後に異なる箇所の修理が必要になることがあります。
例えば、シャッターユニット交換に8万円、半年後にミラーボックス修理に6万円、さらに3ヶ月後に電子回路基板交換に12万円という具合に、結局20万円以上の修理費用が発生するケースがあります。
そうなった場合、同等性能の新品カメラの購入費用を上回ることが多く、経済的に非合理的な選択となります。普段からカメラの調子を確認し、不具合を感じたら素早く対処することで無駄な出費を抑えられます。
事故や怪我のリスクにつながる
過度な発熱やショートによって思わぬ火災につながる可能性も否定できません。特に屋外で長時間カメラを放置する場合、異常な高温状態になりやすいため、普段から安全面にも十分配慮する必要があります。
例えば、バッテリーの異常発熱や膨張は、火災や爆発といった大きな事故を引き起こす可能性があります。リチウムイオンバッテリーの内部構造が劣化すると、電解液の漏出や内部ショートにより急激な発熱が発生し、最悪の場合は炎上します。
電気系統の漏電は、感電事故や電子機器の損傷を引き起こします。カメラ内部の絶縁材劣化や配線の損傷により、本体表面に電流が流れることがあります。特に湿度の高い環境や雨天時の撮影では、漏電による感電のリスクが高まります。
その他にも、機械部品の破損による物理的な危険、有害ガスの発生による健康被害など、リスクは複数あります。
カメラの寿命を少しでも長くする方法

日頃の扱い方やメンテナンス次第で、カメラの寿命は大きく変わります。カメラを長く使うためには、保管場所の湿度や温度、そして衝撃からの保護が最も重要なポイントとなります。加えて使用後のメンテナンスも欠かせない作業です。
カメラの寿命を少しでも長くする方法は以下の通りです。
- ・湿気対策を行う
- ・汚れやほこりから守る
- ・衝撃や落下には注意する
- ・定期的にお手入れをする
- ・無理な操作を避ける
ここでは、寿命を延ばすためのポイントを紹介します。
湿気対策を行う
湿気はカメラにとって最も危険な環境要因の一つであり、内部に侵入した水分がカビの繁殖や電子部品の腐食を引き起こします。
カメラ内部でのカビ発生は、レンズエレメント間やミラーボックス内など、メンテナンスが困難な箇所で進行するため、発見時には既に深刻な状態になっていることが多くあります。
有効な湿気対策として、防湿庫やドライボックスを使うことで、カビや電子部品の腐食を防ぐことができます。保管時の湿度は30~50%をキープするのが理想で、梅雨や夏場の高湿度環境には特に注意が必要です。
シリカゲル乾燥剤の活用も、コストパフォーマンスに優れた湿気対策です。カメラバッグや保管ケース内に適切な量のシリカゲルを配置することで、局所的な湿度制御が可能になります。
汚れやほこりから守る
レンズ表面への汚れ付着は、光学性能の直接的な劣化要因となります。指紋や皮脂汚れに含まれる酸性成分は、レンズコーティングを化学的に侵食し、永続的な曇りや斑点を形成します。
一度劣化したコーティングは再生不可能で、レンズ交換が必要になる場合があるため、注意が必要です。
撮影後はレンズやカメラボディに付いたほこりを、ブロアーや柔らかいブラシで落としてからクリーニングクロスで拭くと良いです。細かな砂やホコリが入り込むとレンズ表面に傷を付ける原因となり、画質の低下や故障につながります。
保護フィルターの使用も効果的です。UVフィルターやプロテクトフィルターをレンズ前面に装着することで、汚れや衝撃からレンズを保護できます。
高品質なフィルターなら光学性能への影響は最小限に抑えられ、フィルター交換により常に清潔な撮影環境を維持できます。
衝撃や落下には注意する
思わぬ落下事故はカメラ内部の精密機器に大きなダメージを与え、修理が困難になるケースも少なくありません。撮影中にストラップをしっかりと使い、カメラバッグにはクッション材を入れるなど、物理的な衝撃をできるだけ抑えることが重要です。
ストラップについては、ネックストラップやハンドストラップを正しく装着することで、手から滑り落ちた際の衝撃を防げます。特に、重量のある望遠レンズを装着した状態では、レンズ側にもストラップを取り付けることで、バランス保持が可能になります。
カメラバッグに収納時は、レンズとカメラ本体を分離して収納し、それぞれを独立したクッション区画で保護することで、相互の衝突による損傷を防げます。航空機での移動時は、機内持ち込みにすることで、荷物の投げ込みによる衝撃を避けられます。
定期的にお手入れをする
レンズだけでなく、センサーやボディの接合部など見落としがちな箇所も適宜クリーニングするべきです。大がかりなメンテナンスはメーカーに依頼する手もありますが、日常的な点検と軽い清掃を習慣づけるだけでも故障リスクの低減に効果的です。
外装部分の清掃は、専用のクリーニング液を使用した定期的な清拭により、素材の劣化を遅らせ、快適な操作感を長期間維持できます。
端子カバーやメモリーカードスロット周辺の汚れは、防塵防滴性能の低下を招くため、歯ブラシなどを使用した細部の清掃が重要です。
接点部分のメンテナンスは、月1回程度の頻度で、接点クリーナーと綿棒を使用した清掃を行うことで、良好な電気的接触を維持できます。
レンズクリーニングは、ブロアーでレンズ表面のほこりを除去し、レンズペーパーまたはマイクロファイバークロスで円周方向に清拭します。
無理な操作を避ける
湿った手で操作したり、シャッターボタンを強く叩くように押したりするなど、乱暴な扱いが機材に負担をかける場合があります。
強制的なレンズ操作は、精密な駆動機構に重大なダメージを与えます。オートフォーカス動作中にフォーカスリングを手動で回転させると、内部のギア機構に過大な負荷がかかり、歯車の欠けや駆動モーターの損傷が発生します。
電子接点への過度な負荷は、通信系統の損傷を引き起こします。レンズ装着時に斜めに挿入したり、固定される前に電源を投入したりすることで、接点間の接触不良が発生します。
バッテリーの不適切な取り扱いは、電源系統全体に悪影響を与えます。端子の向きを間違えて無理やり挿入すると、カメラ側の電源回路が損傷することがあります。
ズーム機構が重く感じたら無理に動かそうとせず、一度点検や清掃を行ってから慎重に使用します。
寿命を迎えたカメラの4つの選択肢

カメラが寿命を迎えた場合でも、処分方法は複数あります。不要になったカメラをどうするかは、資源の有効活用やコスト面で検討する必要があります。新しいカメラへの移行をスムーズにするためにも、適切な選択肢を検討してみると良いです。
寿命を迎えたカメラの処分方法は以下の通りです。
- ・自分で処分する
- ・修理する
- ・友人や知人などに譲る
- ・買取に出す
ここでは、これらの選択肢について詳しく解説します。
自分で処分する
自治体によってはカメラを粗大ごみや不燃ごみとして回収しているところもあります。まずは地域のルールを確認し、分解が必要かどうかを確かめます。環境負荷を考えて、小型家電リサイクルなど適切な処理ルートを選択することが望ましいです。
一般廃棄物としての処分の場合、カメラは小型家電に分類されることが多く、燃えないゴミまたは金属ゴミとして収集されます。
分類は自治体によって異なり、例えば横浜市では30cm以下の小型家電として無料回収していますが、大阪市では金属ゴミとして月2回の収集日に出す必要があります。
小型家電リサイクル法に基づく回収システムの利用は、環境配慮型の処分方法として推奨されています。全国の家電量販店や公共施設に設置された回収ボックスを利用することで、貴金属やレアメタルの再資源化が可能になります。
修理する
メーカーや専門業者による修理は、愛着のあるカメラを長く使い続けたい人にとって魅力的な選択肢です。しかし修理費用が高額になる場合もあるため、新品や中古品を購入するのと比較してコストパフォーマンスを検討する必要があります。
基本的な診断料は3,000円から5,000円程度で、この段階で修理可能性と概算費用が判明します。
一般的な修理費用の目安として、シャッターユニット交換は3万円~6万円、ミラーボックス修理は3万円~5万円、電子回路基板交換は3万円~10万円程度が相場となっています。
これらの費用に加えて、往復送料2,000円程度、作業期間中の代替機レンタル費用の1日1,000円~3,000円程度も考慮する必要があります。修理費用が同等性能の中古機材価格の70%を超える場合、経済的合理性は低くなります。
友人や知人などに譲る
故障の程度が軽微であれば、カメラを必要としている人に譲ることで再利用につながります。
譲渡する際は、相手のスキルレベルに合わせたカメラを選ぶことが大切です。初心者向けのエントリーモデルは操作が簡単で、写真を始めたい友人への譲渡に適しています。
一方、上級者向けの高機能モデルは設定項目が多く、ある程度の経験者でないと機能を十分に活用できません。
相手の撮影目的も考慮要素となり、スポーツ撮影に興味がある人には高速連写機能を持つモデル、風景撮影が好みの人には高画素機種が喜ばれます。
譲る際にはレンズやバッテリーの状態、使い方などを正直に伝え、相手が安心して受け取れるように配慮することが大切です。軽微な不具合でも事前に伝えておくことで、後日のトラブルを避けられます。
買取に出す
古いモデルでも、コレクターズアイテムとしての価値や、専門業者が部品取り用に欲しているケースもあるため、意外な価格が付くことがあります。
買取相場の事前調査により、適正な取引価格を把握できます。一般的に、デジタルカメラの買取価格は新品価格の20%~30%程度となり、発売からの経過年数、人気度、状態により大きく変動します。
発売から1年以内の最新機種では新品価格の50%前後の買取価格も期待できますが、5年以上経過した機種では10%以下になることも珍しくありません。
価格.comやカカクコムなどの価格比較サイトで現在の中古販売価格を確認し、その20%~40%程度が買取価格の目安となります。
上記はあくまでも目安なので、無料査定を依頼し、その結果を踏まえて他の方法と比較検討するとよいです。
買取ウリエルではカメラの無料査定を実施しております!

もし買い替えや処分を検討されているなら、専門業者の無料査定を利用するのもおすすめです。買取ウリエルなら、一眼レフカメラ、ミラーレスカメラなど、あらゆる種類のカメラを適正価格で買取いたします。
カメラは機種や状態によって買取価格が大きく変動します。無料査定サービスを利用すれば、気軽におおよその価値を知ることができ、買い替え時の予算計画にも役立ちます。
大切に使ってきたカメラだからこそ、納得のいく形で次のステップに進めるように無料査定を上手に活用してみてください。
まとめ
一眼レフやミラーレス、コンパクトカメラなど、それぞれの特徴を押さえた上で日頃からケアを行うことで、性能の低下を最小限に抑えることができます。寿命を迎えたカメラは使い続けるとリスクが高まるため、買い替えも視野に入れておくと良いです。
使わなくなったカメラをお持ちでしたら、ぜひ買取専門店ウリエルにご相談ください。カメラの専門知識を持つ査定士が、適正価格での買取をいたします。無料査定も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2つの買取方法