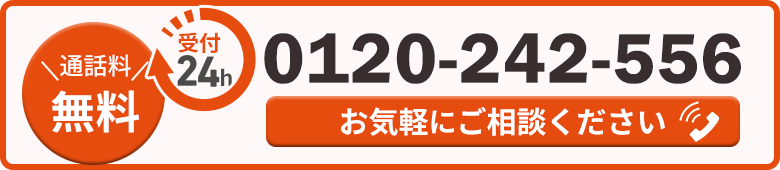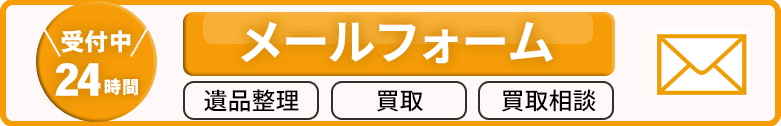織部焼の買取相場!高く売れる織部焼の特徴や少しでも高く売るコツも解説!

織部焼は、桃山時代から江戸時代初期にかけて美濃地方で生まれた陶器として、国内外で高く評価されています。
本記事では織部焼の買取相場をはじめ、高価査定されやすい織部焼の特徴をご紹介します。
ご自宅にある織部焼を少しでも高く売るコツについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
なお、累計買取実績数300万点超えのウリエルでは、織部焼の無料査定を実施中。査定をご検討の方は以下のメールや電話からお気軽にご相談ください。豊富な知識と確かな目利きを持つ査定士があなたのお品物の価値を正確に査定いたします。

ウリエル 商品管理スペシャリスト
河合拓治
リユース業界で12年のキャリアを持ち、現在は買取ウリエルのロジスティクスセンター責任者として年間数万点に及ぶ商品の流通・管理を統括しています。リユース検定や酒類販売管理者の資格を保持し、特にダイヤモンド・ブランド品・着物の管理体制構築に精通。
現場では「複数人による多角的な検品」を徹底し、個品管理による匂い移り防止や破損対策など、商品の価値を損なわないためのオペレーションを追求しています。物流コストの最適化を通じて、お客様への還元率向上に貢献することを目指しています。
監修者の詳細はこちら
織部焼の買取相場

| 種類 | 買取相場 |
| 碗 鯉江 良二 | ~5万円 |
| 青織部花生 岡部嶺男 | ~10万円 |
| ロスオリベ茶碗 鈴木五郎 | ~20万円 |
| 織部菊平向 五 北大路魯山人 | ~30万円 |
※相場は目安であり、買取価格をお約束するものではございません。
織部焼は、時代や作家、保存状態によって大きく価格が変動します。
買取市場では~数十万円で取引されていますが、著名な作家の作品はこれ以上の価格も見込まれます。
特に北大路魯山人や岡部嶺男などの巨匠が制作した作品は、多くのコレクターに人気があるため、オークションや骨董市で高額落札されるケースが少なくありません。
実際の査定価格は実物を見た上での総合的な判断となるため、まずは専門業者に相談することが大切です。
買取相場が高い織部焼の有名作家一覧

織部焼の魅力を大きく左右するのが作家の個性や技術力です。著名な作家の作品は、伝統的な織部焼の特徴を継承しながらも、独自の芸術性を表現しています。
以下にご紹介する作家作品は国内のみならず海外でも評価が高く、高価買取になりやすいです。
- ・岡部嶺男
- ・鈴木五郎
- ・鈴木徹
- ・鯉江良二
- ・北大路魯山人
- ・古田織部
ここでは、これら6名の作家のそれぞれの作風や特徴を解説していきます。
岡部嶺男(おかべ みねお)
岡部嶺男は、織部と青磁の美を融合させた革新的な陶芸家です。父は名陶芸家・加藤唐九郎であり、嶺男はその伝統を継ぎながらも、自身の美意識を投影した作品を追求し、現代陶芸に新風を吹き込みました。
代表作に、縄文的な線文を施した織部茶碗や「粉青瓷」「翠青瓷」と呼ばれるシリーズがあります。これらは日本伝統工芸の中でもとりわけ美術性が高いと評価されている作品です。
市場ではその個性的なフォルムや美しい色合いが高く評価され、高額査定に結びつきやすい傾向があります。
鈴木五郎(すずき ごろう)
鈴木五郎は、美濃の伝統と現代感覚を融合させた個性的な織部焼の名匠です。「人のやらないことをやる」を信条とし、茶碗や鉢といった実用器から前衛的な造形作品まで幅広く手がけてきました。
1995年に発表した「織部椅子」は、座れない構造で作られた異色の作品です。「肉体ではなく、肉体の中に潜むものを座らせる椅子」として、鈴木五郎の哲学的な芸術観を象徴する代表作です。
国内外での評価も高く、市場での需給バランスが買取相場を押し上げています。
鈴木徹(すずき てつ)
鈴木徹は、現代的感性と伝統技法を融合させた織部作家です。銅緑釉を中心に、彫りや塗りを生かした作品づくりを行っており、従来の織部とは一線を画した立体感と躍動感を持つ作品が特徴です。
代表作には、「緑釉花器」や「三彩鉢」などがあり、繊細でありながら力強さを感じさせます。日本伝統工芸展などでの受賞歴も多く、その高い技術力と表現力は多くの専門家から評価されています。
鈴木徹の作品は、美術性と実用性を兼ね備えており、近年の現代陶芸市場でも需要が高まっています。
鯉江良二(こいえ りょうじ)
鯉江良二は、社会や命の問題に切り込むメッセージ性の強い作品で注目されてきた陶芸家です。単なる“うつわ”にとどまらず、現代社会への問いかけを込めたコンセプチュアルな作品が特徴です。
代表作には、反核を題材にした「チェルノブイリシリーズ」や、自身の顔を型取った「土に還る」シリーズがあります。これらは、核問題や生まれ変わりをテーマにしており、いずれも陶芸を通じた強い思想性が感じられます。
その前衛性ゆえにコレクターからの支持が強く、安定した市場価値があります。
北大路魯山人(きたおおじ ろさんじん)
北大路魯山人は、料理人や芸術家など多岐にわたる活躍で知られる存在です。陶芸においては大胆で美しい形状、濃厚な緑釉、そして芸術としての器づくりを実践し、鑑賞用としても実用品としても完璧な美を追求しました。
代表作に「織部釉長板鉢」「織部魚鱗文俎板角鉢」などがあり、いずれも魯山人独自の感性が光る逸品です。
魯山人の作品は、数百万円単位で取引されることもあり、芸術的・資産的価値の両面で極めて高い評価を受けています。
古田織部(ふるた おりべ)
古田織部は、織部焼の創始者といわれる桃山時代の武将で、日本陶芸史に名を残す革新者です。千利休の高弟として茶の湯を学び、「利休七哲」の一人と称されましたが、やがて自らの感性を貫いた「織部好み」を確立しました。
当時は左右対称や整った形が美の基準とされていましたが、織部はその常識を打ち破り、非対称で歪んだフォルムや緑釉による斬新な美を提唱しました。
残存する古田織部の作品は極めて希少であり、歴史的価値も相まって非常に高額で取引されます。
高価買取につながりやすい織部焼の特徴

織部焼の中でも特に高価買取が期待できる作品には、以下のような共通点があります。
- ・桃山時代から江戸時代初期の作品
- ・著名な作家の作品
- ・保存状態のいい作品
- ・共箱・共布・鑑定書などの付属品がそろっている作品
ここでは、主に作品の時代的背景と作家性、保存状態の項目に分けて、どのようなポイントが査定額を左右するのかをご紹介します。
桃山時代から江戸時代初期の作品
桃山時代から江戸時代初期は織部焼の創成期にあたり、古田織部やその弟子たちによって生み出されたオリジナル作品が含まれています。
現存数が非常に少なく、歴史的価値も高いことから、骨董市場では特別視されています。特に古田織部ゆかりの作品は博物館級とされ、現代でも研究対象となるほどの芸術的意義を持ちます。
そのため、桃山〜江戸初期の織部焼は「ただの古い焼き物」ではなく、貴重な文化財として高額査定されるのです。
著名な作家の作品
作家の知名度や受賞歴があることで、作品の価値に確かな裏付けが生まれます。
たとえば、国内外で高く評価されてきた鈴木五郎の茶碗や、食文化と美術の両面で名を馳せた北大路魯山人の器は、美術品としての完成度が高いことで知られています。実際に、オークションでは〜数百万円の値がつくこともあります。
このように、著名作家の作品は“名前”がそのまま査定額に直結する要素となるため、高価買取が期待できるのです。さらに、銘や作家印が明確で、作品の真正性が証明できるケースほど高額査定に結びつきやすいです。
保存状態のいい作品
せっかくの名品であっても、割れや欠け、色落ちなどのダメージがあると美術品としての“完成度”が落ちるため、査定額は低くなる傾向があります。
同じ作家の同じ時代の作品であっても、無傷のものとヒビがあるものでは、査定額に数万円以上の差がつくケースもあります。
器の内外に亀裂や大きな汚れが見られず、当時の美しい釉薬や造形を保っているほど高評価を得やすいです。査定に出す前から、適切な保管や取り扱いを心がけましょう。
共箱・共布・鑑定書などの付属品がそろっている作品
共箱や鑑定書などの付属品がそろっている織部焼は、査定額が大きくアップする傾向にあります。
箱書きがあると作家名や落款が明確になり、作品の信頼度が高まります。ある作品では、共箱付きかどうかで買取価格が数倍変わったという事例もあり、骨董業者も「付属品ありは強み」と明言しています。
つまり、付属品がそろっているだけで、作品全体の価値が高まり、高価買取につながるのです。付属品の有無が査定額の上下を決定づけることも多いので、手元にある場合は必ず一緒に提出しましょう。
織部焼を少しでも高く売るコツ

織部焼を売るなら、できるだけ高く評価されたいものです。そのためには、作品の相場をある程度把握しておくことや信頼できる買取業者を選ぶことが大切です。
ここでは、査定額アップにつながる5つのポイントをわかりやすくご紹介します。
- ・作品の情報を集める
- ・付属品は一緒に査定に出す
- ・作品の保存状態を保つ
- ・織部焼に詳しい買取業者に依頼する
- ・出張買取を利用する
ちょっとしたコツを押さえるだけで、数万円以上の差が出ることもあるのでぜひチェックしてみてください。
作品の情報を集める
作家名や制作年代、入手経路など、わかる範囲で情報をそろえておきましょう。骨董品は贋作も多く、査定の際は作品の信頼性を確認する目的で「どこで誰からいつ入手したか」といった来歴が重視されます。
たとえば「信頼できる専門店で購入した」などの情報があると、作品の価値判断に説得力が生まれ、高額査定につながりやすくなります。
入手経路や記録は立派な評価材料になります。情報が不完全でも、わかる範囲で提供することが大切です。
付属品は一緒に査定に出す
共箱や鑑定書、作家のサインが記された資料などは、作品の真贋を含めた評価を確かなものにします。
とくに共箱は、箱のふた裏などには作品名や作家名が記されており、真作の裏付けとして非常に高く評価されます。
付属品があるだけで大幅に査定額が変わるケースも多いため、手元にある場合は必ず一緒に査定に出すことをおすすめします。買取後の再販時にも購入者にとって優位な情報となるため、業者も高い評価をつけやすくなります。
作品の保存状態を保つ
ヒビやカケ、汚れがあると査定額が大きく下がるため、保管環境を整えることが高額査定につながります。
陶器は桐箱や硬質紙箱に収め、天然素材の布で包んで保管すると傷が防げます。特に「うこん布」は保護性に優れ、見栄えも良いです。
長期保管する場合は、湿度や直射日光にも注意し、たまに開封して状態確認するのも大切なポイントです。少しの工夫で保存状態を良好に保つことができ、それが織部焼の価値を守り、高価買取につながります。
織部焼に詳しい買取業者に依頼する
織部焼をはじめとする骨董品に知見を持たない業者の場合、適正に評価されない可能性があります。
一方、専門知識がある業者であれば、作品の価値を正当に評価できます。保存状態や付属品の有無などから総合的に判断するため、作家不明の作品から有名作家の作品まで対応できるのです。
そのため、査定に出す際には、織部焼の歴史や成形技法などをきちんと理解している査定士がいるかどうか、事前に確認すると安心です。作品の価値を正しく伝えられる業者選びが、高価買取への第一歩と言えます。
出張買取を利用する
出張買取では専門スタッフが直接作品を確認できるため、写真だけでは伝わりにくい質感や重み、保存状態なども査定に反映されやすくなります。
また、織部焼は割れ物で繊細なため、持ち運びによる破損リスクを避けられる点も安心です。業者が自宅まで査定に来てくれるため、輸送時のリスクが軽減されます。特に大型の陶器や点数が多い場合は、時間の節約にもなります。
出張買取は、作品本来の価値を保ったまま査定してもらえるため、結果的に高価買取につながるのです。
織部焼に関するよくある質問
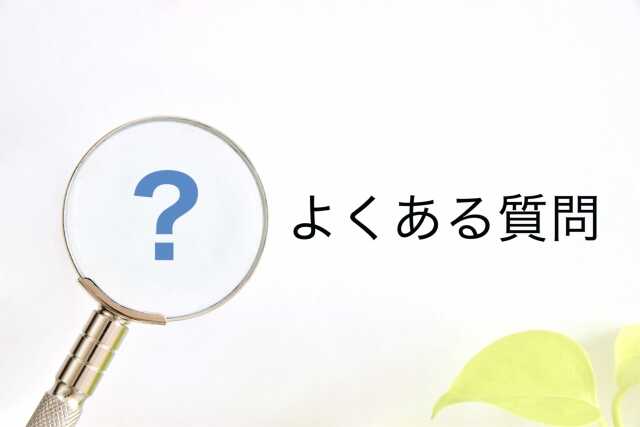
ここでは、織部焼の取引に際して寄せられることの多い質問をまとめました。
織部焼を売買するうえで疑問に感じやすいポイントとしては、本物かどうかの見分け方や、状態が悪いものでも売却可能かなどが挙げられます。
順番に解説します。
織部焼の贋作と本物の見分け方はありますか?
本物の織部焼を見分けるポイントの一つが「共箱の有無」です。共箱とは、その作品のために作家自身が用意した木箱で、箱の蓋の裏などに作家名や作品名が墨書きされています。
これは作家が自作を証明した“真作の証”とも言えます。また、鑑定書や購入時の記録なども、信頼性を示す重要な資料です。
とくに北大路魯山人のような有名作家の作品は贋作が多いため、付属品の有無が買取額に大きく影響します。こうした証拠をそろえたうえで、専門知識をもった査定士に依頼するのが確実です。
遺品整理で出てきた織部焼も買い取ってもらえますか?
遺品整理などで思わぬ名品や希少作品が出てくることは珍しくありません。特に、織部焼は古美術市場で評価が高く、素人目では価値がわからない場合でも、高額査定につながることがあります。
たとえ作家情報や箱書きが不明でも、査定士が実物を確認したうえで気づく点があるかもしれないので、一度査定に出してみるのも良いでしょう。
ただし、遺品は相続財産となるため、相続人や親族と話し合いながら査定や売却の手続きを進めることが大切です。
状態の悪い織部焼も買い取ってもらえますか?
欠けやひび割れ、焼きの変色など、状態の悪い織部焼であっても買取は可能な場合が多いです。
ただし、修復の難しさや見栄えの問題から査定額は下がる傾向にあります。中には歴史的価値の高さから破損していても評価される作品もあるので、あきらめずに専門家に査定を依頼するのが良いでしょう。
なお、将来的に売却を考えている場合は、直射日光や湿気を避けて保管し、衝撃や摩擦を防ぐ工夫が大切です。正しい保存状態を保ち、作品の価値を守りましょう。
織部焼の無料査定は買取ウリエルにお任せください!

買取ウリエルでは、織部焼をはじめとした多数の陶器を取り扱っています。長年の経験をもった査定士が、作品の保存状態や付属品の有無などを総合的に評価し、適正な査定額をご提案いたします。
また、無料で出張買取も実施しております。出張料・査定料・キャンセル料など一切いただいておりませんので、安心してご利用いただけます。
少しでも高額査定を目指したい方は、まずはご自身の織部焼の価値がどれくらいなのかを確かめてみてはいかがでしょうか。
まとめ
歴史ある織部焼は、時代や作家をはじめとしたさまざまな要素によって価値が大きく左右されます。
まずは作品の特徴を理解し、必要な情報を整理して査定に臨むことが高価買取への近道です。複数社を比較し、織部焼をはじめとする陶器の買取に精通した買取業者を選ぶことも忘れずに心がけましょう。
買取ウリエルでの陶器の買取実績は、以下のボタンよりご確認いただけますので、ぜひチェックしてみてください。
2つの買取方法